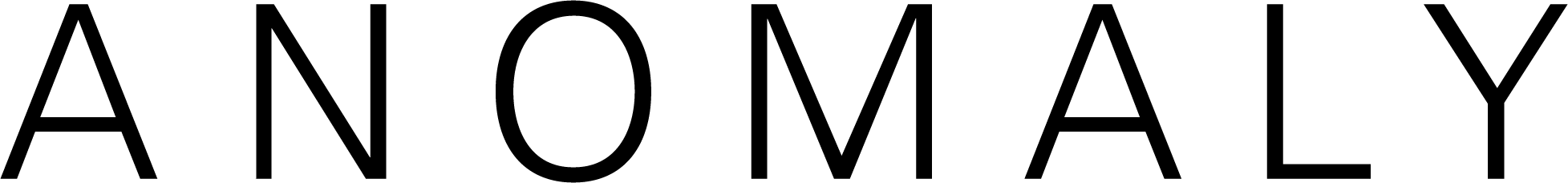
< 伊藤亜紗テキスト 「ゾ・ン・ビ・タ・ウ・ン」 >
消去
この世に消せるものなどあるのだろうか?
たとえば紙に鉛筆で「麻婆豆腐」と書いたとする。これを消す方法を考えてみよう。
① まずはシンプルに消しゴムで消す方法。確かに見た限り紙は白紙に戻ったように見える。しかし消しゴムのカスが残っている。消しゴムで文字をこするとは、「麻婆豆腐」をゴムで包み込んで紙の繊維から引きはがすことである。引きはがしたのであって消したのではない。「麻婆豆腐」を構成していた黒鉛はゴムと一体となり、カスとして机の上に残る。紙+麻婆豆腐(黒鉛)からゴム+麻婆豆腐(黒鉛)への、組み合わせの変化にすぎない。
② 紙を燃やす方法。消しゴムで消すのとは違ってここでは化学的な反応が起こる。しかしこれも組み合わせの変化であることには変わらない。紙は灰になって飛んでいくかもしれないが、消えてなくなるわけではない。
③ 物理的に消せないのであれば、意味的に消してはどうか。たとえば「麻婆豆腐」のあとに、「なし」と書き足す場合。シチュエーションとしては、冷蔵庫に豆腐がないことに気づいた中華料理店の店主が、メニューに書き足すときなどが考えられる。しかしこの方法も、その店にいまは麻婆豆腐がないことを示すのには成功しているが、メニューとしてはあるという事実は消えていない。むしろ、売り切れになるくらいこの店の麻婆豆腐は旨いのだという証拠として、麻婆豆腐の存在感を高める結果にさえなるだろう。
* ①〜③のすべてにかかわる本質的な問題は、「麻婆豆腐」という文字を見た瞬間、人は反射的に麻婆豆腐の味を思い浮かべてしまうということである。同時に見た目も思い出すだろうが、味は見た目よりもやっかいだ。いったん味を思い浮かべてしまうと、「舌が麻婆豆腐の味になって」しまい、知らず知らずのうちに、その日の夕食に麻婆豆腐を食べていた、などということさえありえる。麻婆豆腐を消すことを考えていたのに、むしろ補完してしまうわけだ。「なし」と論理的に否定されても、思い浮かべたその身体的な経験を消すことはできない。認識する者に身体がある限り、消すことは不可能なのかもしれない。
④「麻婆豆腐」のとなりに「麻爺豆腐」と書き足す方法。人の目は似たものを見るとその違いを瞬時に見きわめようとする傾向がある。この傾向を利用して、麻婆豆腐の味を思い浮かべるより先に、文脈をまちがいさがしクイズに変えてしまおうという意図だ。確かに麻婆豆腐という言葉の意味は一時的に棚上げにされるが、意味の問題が文字の問題にスライドしたにすぎず、さらには「お婆さんとお爺さん」という別の意味系が立ち上がってしまう。連想は「日本昔ばなし」と結びつくかもしれない。しかし連想は長持ちしないだろう。いずれ意識は「麻婆豆腐」に帰っていくはずだ。
もちろん消しゴムで文字を消すことを「消えた」とみなし、「なし」と付け加えることをメニューから「消した」ことにしたからといって、とくに問題はおこらない。むしろ、そのときそのときに応じた目の粗さが、日常生活のエコノミーを成り立たせているのだから。しかし厳密にいえば、何も消えていないし、何も消すことはできないのである。
ーーー
リメイク
リメイクとは、再び作ることであり、作るを重ねることである。過去の「作る」を消さずに新しい「作る」が書き込まれていき、この履歴の蓄積こそ、リメイク品をリサイクル品から区別する特徴である。(リサイクルにおいては、古紙がトイレットペーパーに生まれ変わる場合にそうであるように、もとの形は溶けてなくなってしまう。)リメイク品は、いわば前世を残したまま現世を生きるわけだ。前世と現世が物を通して串刺しにされ、ダブルイメージが形成される。もちろん、この世のすべての物は原理的には「作り直された」ものなのである。しかし多くの場合は「履歴」が見えにくくなっている。この意味で、リメイク品は、この世における物のあり方を、簡潔に図解したものだと言うことができるだろう。小林耕平の制作するオブジェにも、ホースや傘といった日用品をリメイクしたものが多い。
ところで、八王子にはあったかホールという施設がある。この施設はゴミ焼却炉に隣接しており、余熱を利用した温水プールや浴場のみならず、毎日ではないが駐車場の脇では足湯のサービスも行われている。このあったかホールの一階に、リメイクをテーマにした工房がある。実際にリメイクを経験するための工房であり、着物の端切れをリメイクして作ったお手玉や、ホースをリメイクした輪投げ、レコード盤とゴルフボールをリメイクして作った独楽などの「作品」が入り口に展示されている。
リメイク品が所狭しとならんでいるその工房では、あらゆるものが二重に見えることになる。特に際立っているのが、机の角、立て看板の角、椅子の背もたれの角、工具入れの角など、さまざまな角にはめこまれた蛍光色のテニスボールである。総数で30個ほどあるだろうか。子供が頭をぶつけて怪我をしないようにという配慮なのだろう。それらはリメイクされて緩衝材となっているが、しかし同時にテニスボールそのものである。その証拠に、工房に足を踏み入れた瞬間、30個ほどの緩衝材=テニスボールが、音も無く一斉にこちらに飛んで来るような感覚におそわれる。というのも、それらの緩衝材=テニスボールは蛍光色であるため周囲の物から浮き上がって見えるうえ、角にかぶせるためにミカンの皮のように切り込みを入れられているため、物に激しくぶつかってバウンドし、衝撃によって楕円形に歪むという、それがテニスボールだったときに有していた弾性が同時に〈再生〉されるのである。加工されたテニスボールというひとつのリメイク品が、〈角を守る〉と〈角に当たって跳ね返る〉という時間的には離れた二つの出来事を結びつけ、過去を呼び覚ました。〈再生〉とはつまり物から出来事がとりだされることである。もっとも、「歪んだボール」というのは肉眼では知覚できないのだから、ここにはマンガ的な表現も同時に〈再生〉されている、と見るべきだろう。ここでは観察者という再生機=プレイヤーの性能が関与している。再生機=プレイヤーはディスク=リメイク品によって〈再生〉されてもいる。
レコード盤とゴルフボールを組み合わせたリメイク品の独楽にも、同様の〈再生〉が起こっている。そのレコード盤は傷だらけだったが、中央部のラベルによれば内容は「ターミネーター2」のものである。盤の中心部の穴にゴルフボールが差し込まれ、これが独楽の脚となるわけだが、実際にまわしてみると、シュワルツネッガー扮するターミネーターが炎を背にこちらに向かって近づいてくる姿が不意に蜃気楼のように〈再生〉されるのがわかる。ここでは「回転」という運動がダブルイメージとなっている。つまり独楽の回転は、同時に、再生機にかけられたレコード盤の回転でもあるのであり、しかしここでは現実の再生機などどこにも存在しないにもかかわらず、映画ターミネーターの有名なワンシーンが、不意に〈再生〉されるのである。〈再生〉とは死んだ物が再び生き返ることだが、たしかにリメイク品にはどこか幽霊的なところがある。前世が現世にとりついているのである。
ーーー
再生
DVDディスクは、映像を物理的な痕跡の列に変換したものである。これにレーザー光をあてると、たとえば映画の物語が〈再生〉される。ディスクという媒体なしでは物語は存在しえず、またディスクに新たな傷を加えれば物語が変わってしまうという意味で、ディスクは物語そのものである。しかし同時に、かたやディスクは物体、かたや物語は時間の要素を含んだ出来事であり、両者は次元の違いを飛び越えて「変換」されたもの、対応しているが全く別のものである。つまり〈再生〉とは、ひとつの物体が実は別のものでもあった、ということが明らかになる事態である。
弾むテニスボールであるかもしれない机の角。回すとターミネーターがやってくるかもしれない独楽。こうした「別のものでもあるかもしれない」という不気味さが、〈再生〉の本質である。止まっていたものが動き出すのが〈再生〉ではない。〈再生〉とは文字どおり死んだものが生き返ることである。つまりゾンビだ。これほど不気味で、魔術的で、不合理なものはない。
この世に消せるものなどなく、したがってあらゆる物体が広義の記憶媒体であるとすれば、DVDディスクのような記憶を目的とする製品でなくても、〈再生〉される可能性はおおいにあるのである。たとえば、道や山や家といった物体も、それが道や山や家でありながら同時に何か別の出来事でもありうるとき、それは〈再生〉されたということができる。教室にいる子供が思い思いに意見を言うように、景色の中にあるさまざまな物体を一斉に〈再生〉させることもできるかもしれない。同時に複数のプレイヤーを動かし、複数の出来事を同時に起こす。
風景の中にあるさまざまな物体が同時に〈再生〉されるとき、その町はゾンビがうごめくゾンビ・タウンになるわけである。人間がいなくなりもぬけの殻になるのがゴースト・タウンであるのに対し、ゾンビ・タウンでは物体そのものが生き返っている。ところで、映画などではしばしば、ゾンビは増殖するものとして描かれている。音楽において複数のプレイヤーによる複数の音源の同時再生がミニマル・ミュージックを生んだように、町においても、〈再生〉されたものと〈再生〉されたもの出会いが、あらたなゾンビを生む可能性がある。身の回りにあるさまざまな対象が別のものであるかもしれない可能性を秘めているのだとしたら、私たちの町は、密かにすでにゾンビ・タウンであるということになる。
ーーー
うずしお
毎年夏休みになると、家族で四国の親戚の家に遊びに行くことになっていた。ドライブは道が空いている年でも七時間はかかり、母が弁当に作ってくれる唐揚げがほぼ唯一の楽しみだった。ところが、もうすぐ鳴門海峡を渡るというところにくると、きまって胸がつまり、唐揚げの肉が喉を通らなくなった。車が淡路島を縦断し、大鳴門橋にさしかかる手前で、毎年同じような息苦しさにおそわれるのだ。親戚の家に行くのが嫌なのではない。確かにあらゆる点で「文化」の違いがあり、一週間のお泊まり生活は子供なりに緊張を強いられたが、そうした異文化体験は同時に好奇心をそそるものだった。
原因は、この先に待ち受けている鳴門海峡にあった。自分はいま家族とともに車に乗り込み、淡路島を縦断し、鳴門海峡大橋を通って、四国へと渡ろうとしている。そのことは理屈としては理解しているのだが、頭は「鳴門海峡を通る」ということになっており、つまり日本地図で見ると非常に狭い淡路島と四国のあいだのわずかの隙間をくぐり抜けて瀬戸内海に入ろうとしていた。なぜそのような実際とは垂直に交わる進路を想像してしまうのか、自分でもよく分からない。イメージは修正できず、鳴門海峡の狭い隙間を何とか突破しなければ、という状況にとらえられてしまうのだ。もともと閉所恐怖症の怪があり、観覧車にもそれが理由で(つまり高所恐怖症のせいではなく)乗ることができないのだが、狭い隙間を通るという状況になると、通っているうちに壁が動いて入り口と出口がふさがり、閉じ込められてしまうのではないかという恐怖におそわれた。この動く壁は体に密着したり離れたりし、まるで食べ物を飲み込む食道のようだった。なるほど、まさにいま自分の食道は唐揚げにぴったりと密着し、それを先へと送ろうし、同時にそれを閉じ込めている。閉所恐怖症の人間の中に閉所があるとは!私はこの先に待つ鳴門海峡に怯えながら、自分の中にある閉所に圧迫され、汗びっしょりになった。迫ってくる淡路島を右手で抑え、左手で重たい四国をのけ、そうやってどうにかこうにか鳴門海峡をこじあけて、辛くも自分の口から外へ脱出する——子供の私の中にあったのはそんな混乱したイメージだった。それが、私が唐揚げの肉を飲み込めなくなる原因だった。
ーーー
タイムトラベル
岡本太郎は生前、「縄文人が自分の真似をしている」とこぼしていたようだ。また似たような話で、最近発表されたある論文が「クラフトワークの元ネタはPerfumeである」という仮説を立てていた。これらの主張に共通しているのは、「起源」は必ずしも過去にあるのではない、という前提である。起源とは「時間的なはじまりの点」ではない。それは「あらゆる可能性が含まれる泉」であって、流れる水がまず見つかり、そのあとに水源が見つかるという場合の方がむしろ多い。岡本太郎は、「縄文的なるもの」の可能性の泉をもっとも深く掘ったのは自分だと考えていたので、縄文人は自分よりも下流にいるように見えたのだ。あるいは論文の著者によれば、クラフトワークの活動を支えていたのはマン・マシーンへの憧憬であったが、そのイメージは日本から来ており、だとすれば日本人によるテクノポップグループであるPerfumeこそが、泉のただなかにいることになる。子のあとに親が生まれる、というわけだ。
だとすれば、現代の社会を構成しているものの起源が、これからやってくる可能性もあるということである。ある町aの起源と称する町Aが百年後に出現するかもしれないし、ジブリ映画よりもジブリ映画らしいたとえば国家が、五千年後にあらわれるかもしれない。自分の元ネタが一万年後に現れる可能性だってあるだろう。その人物は、自分より後に生まれてきたにもかかわらず、自分の存在を先取りしているのだ。
こうした「起源」をめぐる言説を、たんなるレトリックとして片付けることができないのは、自分を含めたあらゆるものが、知らず知らずのうちに、まだ名前すら与えられていない何らかの可能性を、作動させているかもしれないからである。それは、たとえて言うなら、ただ歩いていたつもりなのに、地表面にあったスイッチを踏んでオンにしてしまっていた、というような事態である。現時点において知らず知らずのうちに作動させられた可能性が、未来において意識的に探究され、その探究者が「起源」を自任するに至る。未来にやってくる起源は、現在においては存在していない、少なくとも知られていないものでありながら、現在と関係している何かのことである。それはある意味で、現在が知らず知らずにうちに生んだ結果ともいえる。
文=伊藤亜紗