
惑星のように見る
2025.7.12(土) - 8.9(土)
開廊時間:12:00 – 18:00
日月祝休廊
オープニングレセプション: 7月12日(土)17:00 – 19:00
大木裕之フィルム作品特別上映会&トークイベント:7月26日(土)18:00 – 21:00
登壇者:大木裕之、朝倉芽生(高知県立美術館 学芸員)*敬称略
ANOMALYでは、2025年7月12日(土)から8月9日(土)まで、ギャラリーアーティストと、普段から交流のあるゲストアーティストによるグループ展「惑星のように見る」を開催いたします。
インターネットやソーシャルメディアの発達により、私たちの世界はますます「小さく」なり、常に接続された状態が、日常生活を格段に便利にしました。さらに、GPSなどの位置情報技術の普及により、地球上のどこにいても、高精度な情報を手に入れることが可能となりました。
しかしその一方で、こうしたテクノロジーの発展は、知識や権力の集中を加速させ、社会の分断を生んでいます。また、人間中心主義や経済成長至上主義を助長し、気候変動や地殻変動といった地球規模で起こる長期的な自然の変化から私たちの注意を逸らし、戦争、政治的混乱、環境破壊、生物多様性の喪失など、世界各地で深刻な問題を引き起こす一因となっています。
わたしは惑星(planet)という言葉を地球(globe)という言葉への重ね書きとして提案する。グローバリゼーション[地球全域化]とは、同一の為替システムを地球上のいたるところに押しつけることを意味している。わたしたちは現在、電子化された資本の格子状配列のうちに、緯度線と経度線で覆われた抽象的な球体をつくりあげている。(中略)地球は、わたしたちのコンピューター上に存在している。そこには、だれも暮らしていない。それは、わたしたちがそれをコントロールすることをもくろむことができるかのように、わたしたちに想わせる。これにたいして、惑星は種々の他なるもの(alterity)なかに存在しており、別のシステムに属している。にもかかわらず、わたしたちはそこに住んでいる。*¹
ーガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク『ある学問の死 惑星思考の比較文学へ』
ポストコロニアル・フェミニズム理論で知られる文芸評論家のガヤトリ・C・スピヴァクが提唱した、この「惑星思考」は、20世紀に席巻したグローバリズムを超え、気候、生物多様性、経済、文化などが有機的に絡み合う「地球」を多角的に捉え直す視点です。この考えは、哲学、環境学、社会学などの分野でも引き続き議論されています。
本展では、現代社会における加速度的な変化の中で見過ごされがちな事象や関係性に目を向け直し、⼈間/⾮⼈間や⽂化/⾃然の⼆項対⽴を超えた「⽣」の新たなビジョンの模索や、現在と異なるスケールの時間/空間の想像を可能にし、わたしたちに現実世界を再び鮮やかに感じさせてくれるアーティストたちの視点を通じて、世界を、あらためて「惑星のように見る」*²ことを試みます。
皆様のご来廊を心よりお待ちしております。
青木野枝(b.1958)は、地殻に豊富に存在し、地球全体の重量の約3割を占める「鉄」を素材に抽象彫刻を制作してきました。鉄はまた、私たち哺乳類の血液にも含まれる生命に深く関わる鉱物です。青木は、大気や水蒸気などの無形の存在をモチーフに、鉄が本来持つ硬質感や重量感を超え、彫刻=塊という概念から作品を解き放ち、空間に「変化」や「増殖」といった生命感を呼び起こすような風景を立ち上げます。本展では、2003年より取り組んでいる、積み上げた石鹸を鉄と組み合わせた作品を展示いたします。
近年の主な展覧会に「青木野枝、三嶋りつ惠 そこに光が降りてくる」(東京都庭園美術館、2024)、個展「青木野枝 霧と鉄と山と」(府中市美術館、2019)など。7月19日から長崎県立美術館で開催される「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」に参加予定。

青木野枝《立山》2024年、鉄、石鹸
「そこに光が降りてくる 青木野枝/三嶋りつ惠」東京都庭園美術館(2024)展示風景 撮影:山本糾
淺井裕介(b.1981)は、制作地で採取した土や水を用いて描く「泥絵」、マスキングテープの上からマーカーで描く「マスキング・プラント」、近年では鹿の血液から精製されたプルシアンブルーによる「青い血の絵」など、様々な素材と手法を駆使して絵を描き続けています。また、コロナ禍を機に学生時代から親しんできた陶芸を本格的に再開し、平面と立体を往還する中で、土だからこそ生まれる表現の深度をますます深めています。生命の源である土を用いた作品には、そこに生息していた多様な微生物や、そこから芽吹いた植物が持つ生命力の痕跡が息づき、その土地に生きる生物たちの営みそのものをも内包しています。
近年の主な展覧会に「開館30周年記念 MOTコレクション 9つのプロフィール 1935→2025」(東京都現代美術館、2025)、個展「淺井裕介展 星屑の子どもたち」(金津創作の森美術館、2024)、「横浜美術館 新収蔵作品特別展示 淺井裕介《八百万の森へ》」(横浜美術館、2024)など。現在、金沢21世紀美術館で開催中の「積層する時間:この世界を描くこと」展では、能登半島を中心に石川県内65種類の土を用いて制作された全長約27mにおよぶ壁画を発表している。

淺井裕介《狩を覚えたら遠くまで旅をするのだ》2025年
紙にアクリル、水彩、色鉛筆、鉛筆、インク、H29.7×W42cm
大木裕之(b.1964)は、東京大学工学部建築学科在学中の1980年代前半より映像制作を始めました。1989年からは、北海道松前町を中心に毎年撮影を続ける映像作品群「松前君シリーズ」に取り組んでいます。
カメラを片手に世界各地を巡り、自らの身体を動かし続けるその実践は、移動・生活・哲学の相関関係を探る試みでもあり、複雑に構成される世界の姿を映像として描き出します。膨大なイメージが折り重なる独自かつ詩的な映像表現は高く評価されており、これまでに国内外の国際展や国際映画祭に多数参加。2022年には国立映画アーカイブに作品が収蔵され、2023年にはロンドンのバービカン・センターや香港のM+でも上映されるなど、近年ますます注目を集めています。
本展では、7月26日(土)に、1990年代の貴重なフィルム作品を中心とした特別上映会(デジタル上映)とトークイベントを開催いたします。
1990年に《遊泳禁止》がイメージフォーラム・フェスティバル審査員特別賞、1996年に《HEAVEN-6-BOX》が第46回ベルリン国際映画祭NETPAC賞を受賞。近年の主な展覧会に、「しないでおく、こと。―芸術と生のアナキズム」(豊田市美術館、愛知、2024)など。

大木裕之《乱気流》1991年、シングルチャンネル・ビデオ、43min 6sec
マキ・ナ・カムラは、絵画における「地平線」という視覚装置を、画家が構築したフィクションとして捉え、その先に広がる新たな世界像の可能性を探究しています。最新シリーズ《Desert Incognito》では、鳥や、かつて遊牧騎馬民族だった王など象徴的な存在が登場します。地平線の向こう側、「Desert Incognito」と名付けられたその地で、王は馬にまたがり、高座でくつろぎ、鳥たちはその姿を少し高いところから静かに見守っています。彼らは、私たちの言葉や時間の尺度では語らない、異なる秩序の中に生きる存在です。カムラの絵画は、歴史を単なる「過去の出来事」として断絶するのではなく、現在と地続きのものとして呼び戻し、文明の周縁やその境界にあるものを見つめ直します。そして、私たちがどこから世界を見ているのかを静かに問いかけます。本展では、新作ペインティングを展示いたします。
近年の主な展覧会に個展「Placing Stones, Gleaning Apples」(オストハウス美術館、ハーゲン、ドイツ/ドーン・ダエネーンス美術館、ドゥールレ、ベルギー、2017)など。 現在、ロンドンのMichael Werner Galleryで個展「Desert Incognito」が開催されている。

マキ・ナ・カムラ《Witness of Desert Incognito I》2025年
キャンバスに油彩、テンペラ、H60×W50cm
衣川明子(b.1986)は、世界を構成する全ての生命体の奥に限りなく平等な領域が広がっていると考え、油絵具を擦り付けるようにして薄く何層にも塗り重ねる手法で、ぼんやりと浮かび上がり、ゆっくりと変化、振動する、原子や細胞のような生命の最小単位のイメージを描いています。それは、精神と身体、個と社会といった関係性を探る絵画的実践とも言えるかもしれません。衣川は2023年から一年間、文化庁新進芸術家研修制度によりハワイに滞在、また今年5月には、サンパウロで開催される個展のため、現地制作を行いました。本展では、帰国後に制作した新作ペインティングを展示いたします。
近年の主な展覧会に「project N 83 衣川明子」(東京オペラシティアートギャラリー4Fコリドール、2021)など。 現在、サンパウロのMendes Wood DMで個展「Above the focus, behind the ear」が開催されている。

衣川明子《アオ、アカ》2025年、キャンバスに油彩、H91,5×W73cm
斎藤玲児(b.1987)は、日常的に撮影した膨大な写真や動画を素材に、ナラティヴ(物語性)の発生に抗い、カット間の連続性や関連性を意図的に拒む編集により、独特なモンタージュを生み出す映像作品を制作しています。また、被写体を極端にクローズアップすることで、意味の構造を揺るがし、無効化させる手法も特徴的です。「そしておそらく、この作業によって浮き彫りにされる「世界」の無意味性が、逆説的に、「世界」の無意識のようなものを表象することになるのだ。」*³ 本展では最新の映像作品を展示いたします。
近年の主な上映会に『SCOOLシネマテーク Vol.4 斎藤玲児レトロスペクティブ』(SCHOOL、東京、2024)など。
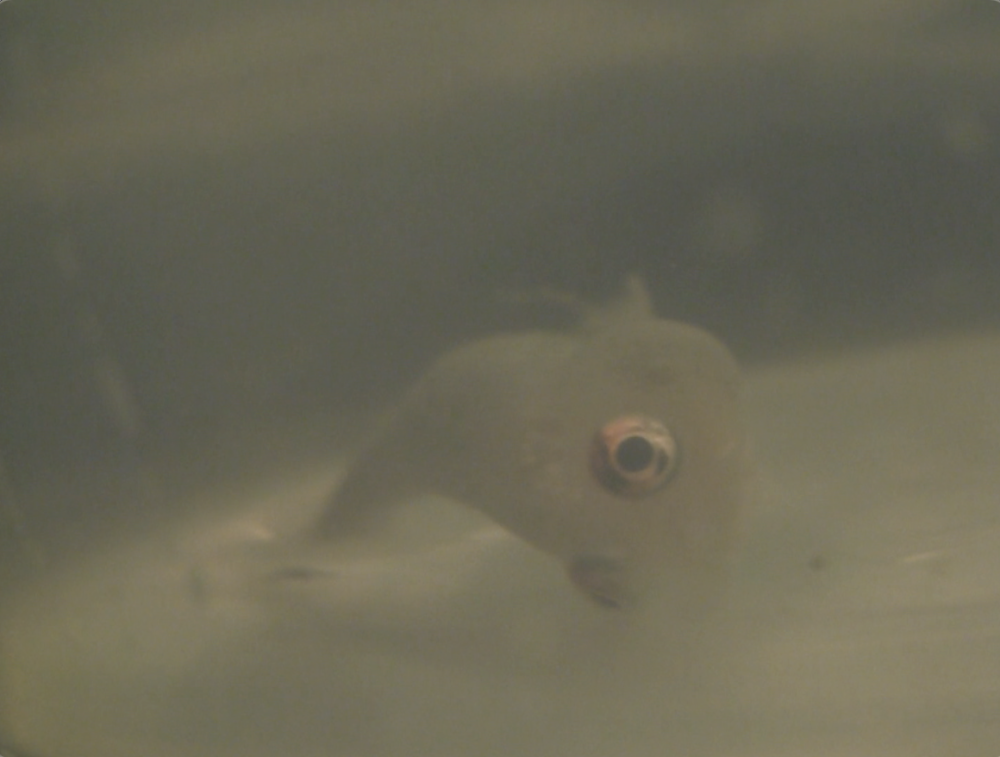
斎藤玲児《32》2024年、シングルチャンネル・ビデオ、26min
佐々木類(b.1984)は、ロニ・ホーンも学んだロードアイランド・スクール・オブ・デザインのガラス科で学び、保存や記録が可能な素材であるガラスを用いて、身近な自然や生活環境から着想を得た作品を制作しています。草花などを採取し、透明なガラスに封入して焼成する行為は、その時々の自分と場所を結びつけ、目に見えない記憶を可視化する試みでもあります。本展では、活動拠点である金沢で採取された植物を用いた《土地の記憶》シリーズ、訪れた土地で採取した植物を用いた《植物の記憶》シリーズ、部屋の隅を型取った《隅》を展示します。
近年の主な展覧会に「コレクション展1」金沢21世紀美術館(石川、2024)個展「Subtle Intimacy: Here and There」ポートランド日本庭園(ポートランド、アメリカ、2023)など。9月13日から「国際芸術祭あいち2025」に参加予定。
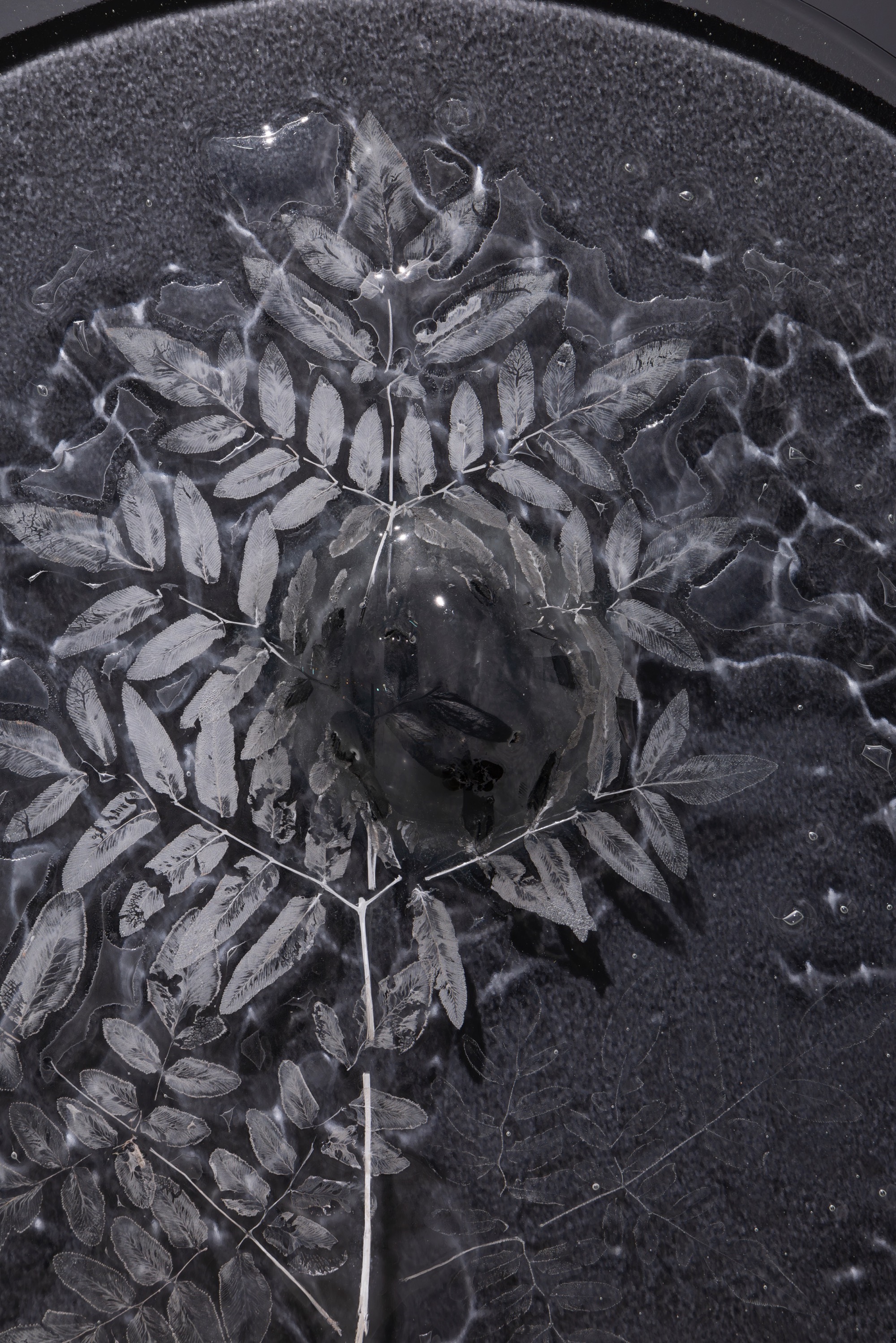
佐々木類《土地の記憶 / 庭掬い_01》2021年(部分)
ガラス、植物、Φ約53.5×0.6cm
長島有里枝(b.1973)は、他者との関係性を見つめることで家族やジェンダー、階級に付与された社会規範を鑑賞者に問い直すような写真作品を制作し、2010年代には女性のライフコースに焦点を当てたインスタレーション作品も数多く発表してきました。
長島の眼差しは、自分自身、家族、ペット、大切な友人や仕事仲間、日常の時間など、身の回りの大切なものに向けられています。2021年に金沢21世紀美術館で開催された「ぎこちない会話への対応策—第三波フェミニズムの視点で」では、ゲストキュレーターとしてアーティストたちと対話を重ねながら展覧会を作り上げました。また、2023年の個展「長島有里枝 ケアの学校」(港まちポットラックビル、名古屋)では、会期中に会場を自身のスタジオとして公開し、アーティストや来場者とともにパフォーマンスやイベントも開催するなど、その表現の幅を大きく広げています。本展では、日常生活や家事の場面を切り取った《家庭について/about home》シリーズ、アメリカ各地でカメラにおさめた植物のシリーズ《wild flowers》、亡くなってしまった愛犬の毛の色と同じ色に染めた髪が印象的なセルフポートレート《You remind me (spring version)》を展示いたします。
近年の主な展覧会に「I’M SO HAPPY YOU ARE HERE – JAPANESE WOMEN PHOTOGRAPHERS FROM THE 1950s TO NOW」(Palais de l’Archevêché、アルル、フランス、2024)など。

長島有里枝《You remind me (spring version)》2022/2025年、Cプリント、image: H43.2×W35.6cm
*This is a variation on the exhibited work.
潘逸舟(b.1987)は、幼少期に上海から青森へと移住した自身の経験を起点に、社会と個人、他者と自己の相互関係や、アイデンティティの在り方を探究し続けています。本展では、オーストラリア・ブリスベンでのフィールドワークをもとに現地で撮影された映像作品《not ocean》(2024年)を展示します。クイーンズランド・アート・ギャラリー&ギャラリー・オブ・モダン・アート(QAGOMA)の協力を得て制作された本作では、重力に抗い、水のない大地で泳ごうともがきながら漂流する身体を通して、居場所を持たない移民の身体が視覚化され、歴史的に搾取されてきた土地における労働とその遺産への批評的視点が浮かび上がります。
近年の主な展覧会に、「ぎこちない会話への対応策―第三波フェミニズの視点で」金沢21世紀美術館(石川、2021-2022)、「ホーム・スイート・ホーム」国立国際美術館(大阪、2023)、「APT11」QAGOMA(ブリスベン、オーストラリア、2024)、個展「アートは美しくなければならない」青森県立美術館(青森、2025)、「Asian Avant-Garde Film Festival 2025: Time Will Tell」M+(香港、2025)ほか国内外の展覧会に多数参加。国立国際美術館にて開催中の「非常の常」展に映像インスタレーションを出展中。
 潘逸舟《Not Ocean》2024年、シングルチャンネル・ビデオ、16min 23sec
潘逸舟《Not Ocean》2024年、シングルチャンネル・ビデオ、16min 23sec
東山詩織(b.1990)は、人と人との間にある外的・内的な境界や、自らの心身を守る無意識/意識的な行為や反応を主題に制作しています。物語などのフィクションや体験談、武器や防具、陣形図、フェンスや生垣、シェルター、遺構などを日常的にリサーチし、和紙やキャンバスに色鉛筆や水彩絵具で精緻に描き出します。塀や壁、生垣、有刺鉄線といった遮断を象徴するモチーフやグリッドを反復的に描く幾何学的な画面構成は、異なるスケールとパースを交錯させ、鑑賞者の意識を深層へと誘います。現代社会が抱える自然災害や地政学的リスクのなかで、私たちはどこに「セイファー・ルーム(より安全な空間)」を見出せるのかーその問いが、不条理な世界への静かな抵抗のかたちとして作品に宿ります。本展では新作平面作品を展示いたします。
近年の主な展覧会に「森の芸術祭 晴れの国・岡山」(グリーナブルヒルゼン、真庭/蒜山エリア、2024)など。

東山詩織《Blue Roofs》2025年、綿布を張ったパネルに白亜地、水彩、色鉛筆、H46×W46cm
樋口亜弥(b.1988)は、クリーム色の皿に載せられた卵や、木の枝にとまる小鳥、朝露に濡れる草花など、日常のささやかな光景を、流れるような筆致で静かに、そして親密に描き出します。曇りガラス越しに見るような、あるいは夢の中にいるような、白くやわらかな光と静けさに満ちた画面は、私たちの日常に潜む神秘性や詩情をそっと浮かび上がらせ、現実をより深く、豊かに捉える視点を提示します。本展では新作ペインティングを展示いたします。
近年の主な展覧会に個展「after the rain」(ARTRO、京都、2025)、個展「In the mountain strong wind」(Union Pacific、ロンドン、2024)など。

樋口亜弥《eggs in the warmlight》2025年、キャンバスに油彩、H24.2×W33.3cm
渡辺豪(b.1975)は、自身の身の回りにある本や食器、部屋などをモチーフに、3DCGを用いた作品の可能性を探求し、身近な風景が物質的な制約や光学的な法則から離れて動き、変化をみせるアニメーションを制作しています。作品がもたらす整合性を欠いた物の在り様や光の振る舞いは、普段自明のものとして見ている世界を撹乱し、私たちが何を見ているのかを静かに問いかけます。近年は展示空間をアニメーションから延長される場所と捉え、複数チャンネルのインスタレーション作品を発表するなど表現の幅を広げています。本展では、急逝した友人に纏わる事物や記憶をモチーフに⼀つの⾵景を組み⽴て、ランダムな光の中に組み込んだアニメーション作品《Tの再構成》と、フィンランドでの研修中に撮影した写真作品を展示いたします。
近年の主な展覧会に、個展「Go Watanabe | M5A5」(グルベキアン現代美術館、リスボン、ポルトガル、2024)など。
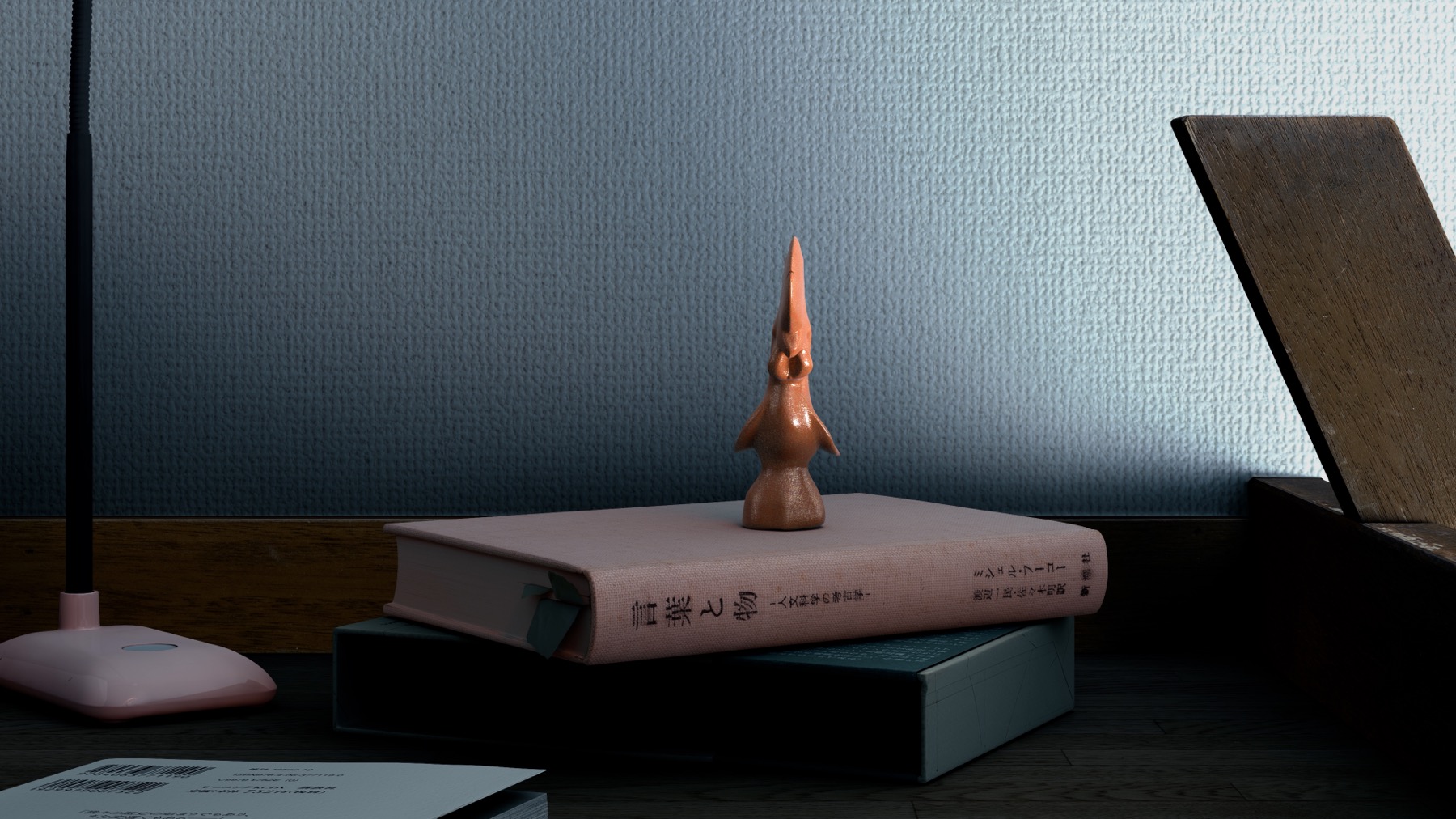
渡辺豪《Tの再構成》2024-25年、4Kアニメーション、Loop (135min 16sec)
註)
*1 ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク『ある学問の死 惑星思考の比較文学へ』上村忠男、鈴木聡訳、みすず書房、2004年、pp.123-124
*2 ジェームズ・ブライドル『WAYS OF BEING 人間以外の知性』岩崎晋也訳、早川書房、2024年、p.164
*3 佐々木敦『アートートロジー』フィルムアート社、2019年、p.113
その他参考書籍:
ヴァージニア・ウルフ『自分ひとりの部屋』片山亜紀訳、平凡社、2015年
ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』鴻巣友季子訳、新潮文庫、2024年
小川公代『ケアする惑星』講談社、2023年
ロレッタ・ナポリオーニ『編むことは力』佐久間裕美子訳、岩波書店、2024年
展覧会概要
展覧会タイトル:「惑星のように見る」
出展作家:青木野枝、淺井裕介、大木裕之、マキ・ナ・カムラ、衣川明子、斎藤玲児、佐々木類、長島有里枝、潘逸舟、東山詩織、樋口亜弥、渡辺豪
会期:2025年7月12 日(土)– 8月9日(土)
時間:12:00 -18:00 休廊日:日曜・月曜・祝日
会場:ANOMALY
協力:Michael Werner Gallery、PGI、Union Pacific
大木裕之フィルム作品特別上映会&トークイベント
日時:7月26日(土)18:00 –21:00
会場:ANOMALY
定員:30名
*7月5日 (土) より、ArtStickerからご予約いただけます。
上映作品:《乱気流》(1991)、《色風》(1991)、《色目》(1992)、《松前君の赤いパブリックパンツ映画》20160703大分mix (1998-2012/2016)
*上映作品には、一部性的表現を含む箇所がございます。あらかじめご理解の上ご視聴ください。
トークイベント:大木裕之 x 朝倉芽生(高知県立美術館 学芸員)*敬称略
































